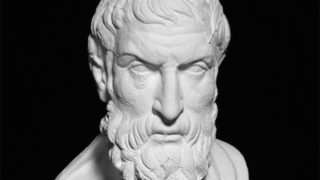キルケゴールの「死に至る病」は難解な哲学書の一つです。名前から惹かれて入り、内容の難しさに挫折した人も多くいることと思います。
たしかに書かれている言葉が遠回しだったり、使われている語句の説明などもないため、何を言っているかわからないと感じられると思います。
しかし、キルケゴールが本書を通じて伝えようとしていることはそんなに難しいことではありません。
今回はそんなキルケゴールの「死に至る病」を図を用いてわかりやすく簡単に解説しようと思います。
Contents
死に至る病は何のために書かれた?
キルケゴールがなぜ「死に至る病」を執筆したかを知ることは、本書の内容を理解することに大きく役立ちます。
「死に至る病」の書かれた目的はというと、、、
読者をキリスト教の信仰へ導くこと。
これが、「死に至る病」の書かれた目的です。ですので、至るところに神を信じること、そしてキリスト教徒であることの素晴らしさが描かれています。
キリスト教徒ではない私たちが本書を理解しにくいと感じる理由の一つはここにあります。
では、キリスト教ではない私たちが読む価値のない本なのかというと、そうではありません。
最終ゴールはキリスト教であり、心から納得できないとしても、それに至るまでの経緯(人間はどのように不安や疎外感、そして絶望を感じるのかの考察)は一読の価値ありです。
キルケゴール自身、生涯において様々な絶望を感じ、その絶望とは何か正面から向き合い考え抜いた人です。
そして真剣に絶望と向き合い、どのように生きるべきかをまとめたのが本書です。
現代を生きる私たちにとっても考えさせられることの多い一冊だと言えます。
キルケゴールの人生

「死に至る病」の内容に入る前に、キルケゴールの生涯を見てみましょう。
キルケゴールがどのような人で、どのような人生を送ったかを知ることは、「死に至る病」を理解する上で必須です。
なぜ、キルケゴールが絶望について考えるようになったのか、なぜ神をそこまで崇拝するのかがわかると思います。
キルケゴール誕生
1813年、キルケゴールはデンマークのコペンハーゲンに7人兄弟の末っ子として生まれます。
当時のデンマークは敬虔深く、規律正しいキリスト教社会でした。
父ミカエルの成功
キルケゴールの父ミカエルはもともとは荒地の農奴で貧しい生活を送っていましたが、伯父の家業を引き継ぎ、コペンハーゲン屈指の大商人となります。
父親の徹底的な倫理教育
兄弟の中でも一際、賢く才能があったキルケゴールは、父親か牧師への道へ進むよう英才教育を受けます。
徹底的な倫理教育により、敬虔なキリスト教徒としての生活を実践していました。
父ミカエルの罪の告白
父ミカエルはある日、キルケゴールに過去の2つの罪を告白します。
1つめは、以前ミカエルが貧しかった時、あまりの生活の過酷さに「私はもう神を信じない!」と神を呪ったことがあるという罪。
2つめは、ミカエルは一度クリスティーネという女性と結婚していたが、子どもができないうちにクリスティーネは肺炎で亡くなりました。
その直後、ミカエルは暴力的に家政婦を犯し、子どもがをできてしまいます。その家政婦がキルケゴールの母親でした。
父ミカエルはこの2つの罪から、自分は呪われていると考えていました。
実際、ミカエルの7人の子どものうち、長男と末っ子のキルケゴールを除いた5人が34歳までに亡くなっており、ミカエルはこれを呪いと捉えていました。
キルケゴールもこの呪いを信じ、自身も34歳までに死ぬものだと確信していました。
退廃的な生活
父の罪の告白を聞き、衝撃を受けたキルケゴールはこれまでの敬虔なキリスト教徒としての生活をやめ、退廃的な生活を送るようになります。
酒屋で飲み明かし、売春宿にも通うようになります。しかし、キルケゴールには性的不能があったと言われており、子孫も残せないのかと更に絶望したとされています。
レギーネとの出会い
そんな中、キルケゴールはレギーネ・オルセンという女性と出会います。
2人は惹かれあい、キルケゴール27歳、レギーネ17歳の時に婚約します。
しかしその1年後、キルケゴールは婚約を破棄してしまいます。理由としては、キルケゴールが自身の呪われた生を確信していたこと、その呪われた生に純粋なレギーネを巻き込みたくないと考えたためと考えられています。
執筆活動の開始
このように様々な経験を経て、キルケゴールは人々の苦悩について深く考えるようになります。
人間が持つこれらの苦悩とは何か、そしてどのように生きればよいのかを突き詰め自分なりの思想を作り上げようと、父の遺産を使って執筆活動を始めました。
キルケゴールの死と死因
その後、様々な著書を残したキルケゴールは42歳の時、道端で倒れ亡くなりました。死因は脳炎だと言われています。
死に至る病の解説
それでは、「死に至る病」の内容を見ていきましょう。
死に至る病とは絶望のことである。
冒頭で死に至る病とは絶望であることが明らかにされます。つまり、本書は絶望について書かれた本であることがわかります。
全体の構造は
- 人間論と絶望
- 絶望の諸形態
- キリスト教的人間論と罪
- 罪の諸形態
以上のようになっています。
はじめにキルケゴールの考える人間論、絶望論が土台として与えられ、次に絶望の具体例がいくつか提示されます。

読者はこの絶望の具体例の中に自分の姿を見つけ、自分自身の絶望と罪を自覚するという流れです。
前半の1.人間論と絶望、2.絶望の諸形態では一般論が述べられます。
後半の3.キリスト教的人間論と罪、4.罪の諸形態では前半の一般論にキリスト教を加えた説明がされます。
神の概念を導入すると人間論=キリスト教的人間論、絶望=罪という構造が現れます。
あくまでもベースは人間論と絶望論です。
では、キルケゴールの人間論と絶望論を見てみましょう。
キルケゴールの人間論
「死に至る病」は人間論から始まります。
そしてこの冒頭が本書一番の難所であり、かつ核となる部分です。
難しいからといって、ここを曖昧なままにして進んでしまうと、その後のパートもちんぷんかんぷんになってしまうので、しっかり意味を理解していきましょう。
人間とは精神である。では、精神とは何か? 精神とは自己である。では自己とは何か? 自己とは関係であるが、関係がそれ自身に関係する関係である。etc,,,
以上が本文から引用です。このような調子でどんどん話が進んでいきます。挫折しそう? 安心してください。できるだけ簡単に解説します。
キルケゴールの人間論は3つのことを言っています
- 人間は、無限性と有限性、時間的なものと永遠なもの、可能性と必然性という2つのものの間の関係(総合)である。
- そうした2つのものの間の関係がそれ自身に関係する時、人間は自己である。
- 人間は自己として他者によって認められた。
一つずつ解説します。
1.人間は、無限性と有限性、時間的なものと永遠なもの、可能性と必然性という2つのものの間の関係(総合)である。

キルケゴールは人間を「無限性ー有限性」、「時間的なものー永遠なもの」、「可能性ー必然性」という2つのものの間の関係として捉えます。
【無限性と有限性】
人間は無限性と有限性を持つ生き物です。
無限性とは「想像力」のことです。有限性とは日々の現実の生活を取り囲む「具体的な物事」のことです。
人間は現実逃避しながら想像の中の世界だけで生きることもできますし、反対に想像力を無くし、日々の現実に埋没しながら生きていくこともできます。
【時間的なものと永遠なもの】
人間は時間的なものと永遠なものを持つ生き物でもあります。
キルケゴールは人間は肉体(時間的なもの)と魂(永遠なもの)でできていると考えています。
【可能性と必然性】
人間は可能性と必然性の中で生きている生き物でもあります。
自分の持って生まれた能力、外見、環境など、既に決められている「必然性」。
その必然性だけで人生がすべて決まってしまう訳ではなく、自由に自分で人生を選んで何にでもなれるという「可能性」。
このように人間は【無限性と有限性】【時間的なものと永遠なもの】【可能性と必然性】の中で生きている存在であるといえます。
想像力を働かして空想の中の世界で生きることもできれば、自分の目の前にある具体的な現実に埋没して生きることもできる。
死んだら全てが無になる存在として生きることもできれば、魂や精神という永遠なものを信じて生きることもできる。
自分に与えられたスペックに従って生きることもできれば、更なる可能性を信じて、挑戦し続けながら生きていくこともできる。
キルケゴールは人間をこのような存在として捉えています。
2.そうした2つのものの間の関係がそれ自身に関係する時、人間は自己である。

ここでいう「関係」は、原語であるデンマーク語の「forholde」から考えると「態度を決する」と訳した方がわかりやすいと思います。
上で見てきたように人間は【無限性と有限性】【時間的なものと永遠なもの】【可能性と必然性】の中で生きている存在です。
これらの関係の中で、どちらに重点を置くか、自ら関係して(態度を決して)生きる時、人間は本物の自己になるとキルケゴールはいいます。
【可能性と必然性】を例にとってみると、元々生まれ持ったスペックに従って限界を受け入れて生きるか、今持っているスペックから目を背け、可能性の中で生きて現実逃避するか。
可能性と必然性のバランスをどの程度にするか自分で態度を決して(関係して)生きていくことで、人間は一つの独立した自己になることができます。
人生や自己について深く考えず、流されながら生きていくこともできます。現代の社会ではむしろこのような人の方が多いのではないでしょうか。
しかし、キルケゴールはどのように生きるか自分で態度を決して生きてこそ、本当の自己になれると説きます。
3.人間は自己として他者によって認められた。
人間は自己として他者によって認められた存在であるとキルケゴールは考えます。
他者とは誰か? 結論から言うと他者とは神です。
つまり人間は神によって認められた存在であるとキルケゴールは考えます。
上で述べたように人間は、2つのものの間の関係の中で自ら態度を決して生きなければなりません。
その際、一人一人の人間には「このように生きるのが、自分にとっては正しい」と言えるような生き方(2つのものの間でのバランスの取り方)があるのではないでしょうか。
そのような「正しい生き方」についての答えを与えてくれる存在、つまり神が存在するとキルケゴールはいいます。
一人一人の人間にとって「あるべき自己のあり方」が存在し、その「正しい自己」を目指して生きることが大切だというのがキルケゴールの考えです。
【キルケゴールの人間論まとめ】
人間は「無限性ー有限性」、「時間的なものー永遠なもの」、「可能性ー必然性」の関係の中で生きており、その関係に対して自ら態度を決めて生きるとき本当の自己となる。また、人間は神によって認められており、神は一人一人の人間に「あるべき自己の姿」を用意している。
キルケゴールの絶望論
ここでは本書のテーマともなっている絶望とは何かについて考えていこうと思います。
まずはじめにキルケゴールが考える絶望の定義を示します。
「絶望とは、それ自身に関係する総合の関係における不協和である。」
不協和=誤った関係ということです。人間は「無限性ー有限性」、「時間的なものー永遠なもの」、「可能性ー必然性」の関係の中で、自ら態度を決して生きていますが、神の意志である「正しい自己のあり方」を顧みることなく、好き勝手な仕方で関係してしまう状態のことを、キルケゴールは「絶望した状態」と呼びます。
言い換えると、神の用意した「正しい関係性」に従って忠実に生きている時は、絶望していないということになります。
神がせっかく「正しい自己のあり方」をそれぞれの人間に示してくれているのに、それを無視して、自分の関係したいように関係して生きてしまうと、心の中で何か違うとモヤモヤが出てくる。これが絶望した状態です。

自分はもっとできると可能性だけを重視して生きていると、実際にできない自分との差にガッカリしてしまう。これは必然性を軽視して可能性を重視しすぎたことで起きている絶望の一種です。
絶望から救われるには
では絶望から救われるにはどうすればよいのでしょうか。キルケゴールの答えはこうです。
「信仰すること」
信仰することとは「神の意志に忠実になろうとすること」です。
苦悩で満ち溢れた世の中で、神の意志に耳を澄ませ、それを体現しようと生きる時、私たちは絶望から解放されるとキルケゴールは説きます。
神の意志に忠実に生きているという安心感を感じて生きている状態が絶望がない状態です。
反対にこの絶望を感じることがないと、人々は神を求めはしないとキルケゴールはいいます。
絶望を感じて初めて、人々はそれから解放されようと神の意志を探し始めるのだと。
絶望は信仰に欠かせないものだと述べて、キルケゴールは本書を締めくくります。
まとめ

以上、キルケゴールの「死に至る病」を解説しました。簡単にまとめます。
- 死に至る病とは絶望のこと。
- 人間は無限性と有限性、時間的なものと永遠なもの、可能性と必然性という2つのものの間の関係の中で生き、自分で態度を決めることができる存在。
- 一人一人の人間に「あるべき姿」が用意されている。
- 「あるべき姿」とズレている時、人間は絶望を感じる。
- 神が用意した「あるべき姿」を求めて生きる時、人間は絶望から解放される。
以上が「死に至る病」でキルケゴールが伝えようとしているテーマです。
本書に挫折してしまった方も、以上を頭の片隅に置いて、もう一度チャレンジしてみて下さい。きっと以前よりすんなり理解できるはずですよ。